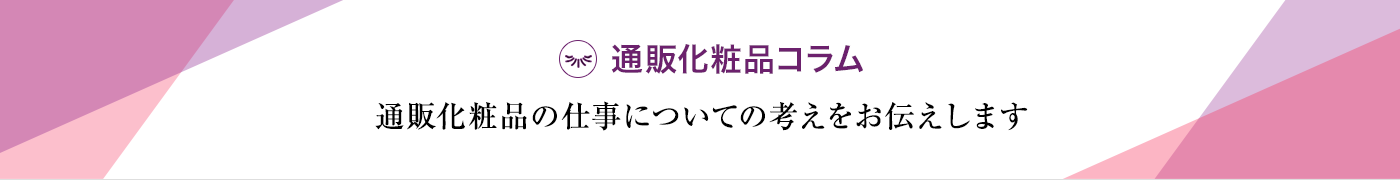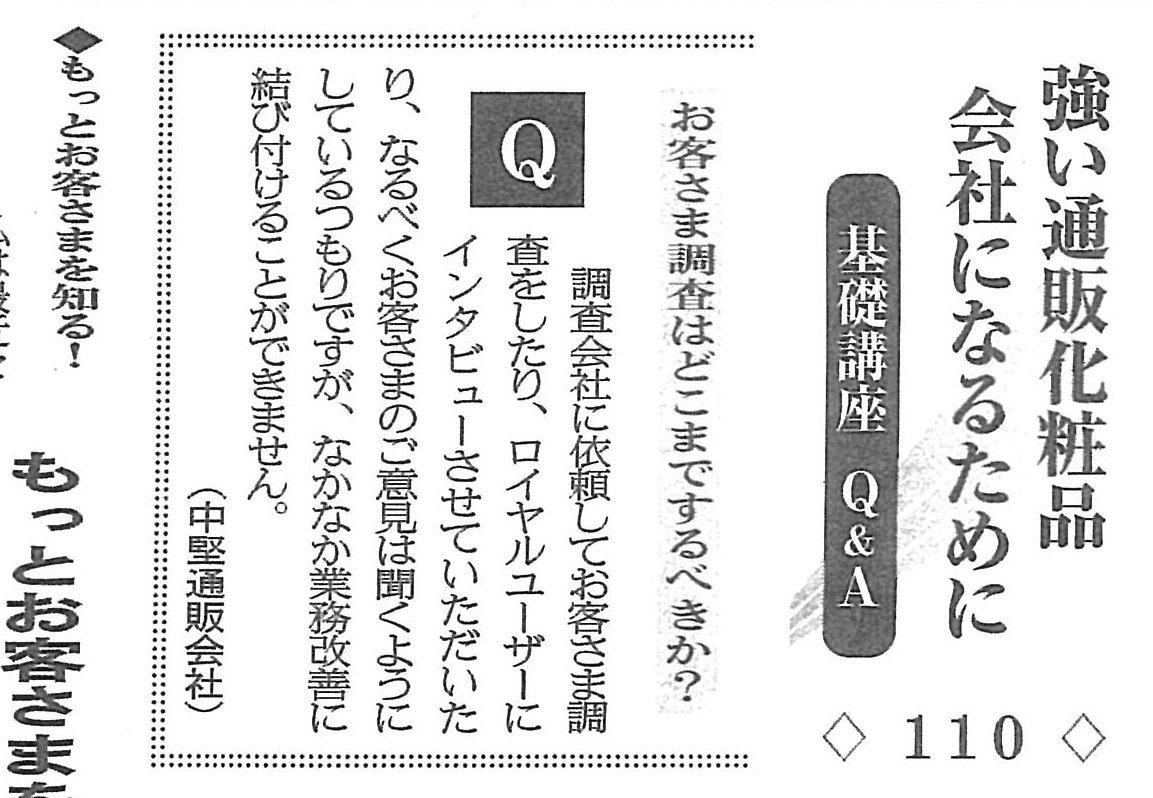「日本流通産業新聞」 1月9日号に、代表取締役 鯉渕の『強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.110 「Q.お客さま調査はどこまでするべきか?」』が掲載されました! 本文は、下記の通り。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q.お客さま調査はどこまでするべきか?
調査会社に依頼してお客さま調査をしたり、ロイヤルユーザーにインタビューさせていただいたり、なるべくお客さまのご意見は聞くようにしているつもりですが、なかなか業務改善に結び付けることができません。
(中堅通販会社)
A.もっとお客さまを知り、お客さま目線で自社の対応と他社動向を分析する
◆もっとお客さまを知る!
私は最近セミナーでお話しをさせていただく時に、必ず最初に「自社のお客さまについてどのくらい知っていますか?」という質問をさせていただくことにしています。当社が主にお手伝いしているのは通販化粧品会社で、直接お客さまにお会いする機会は少ないはずですが、最近は「イベントで会っている」とか「お客さまインタビューをした」といった回答が少し多くなってきました。それでも、毎月定期的にお客さまに会っているか、声を聞いているかなど、細かくヒアリングしていくと、なかなか満足のいく回答は得られません。
私はこの状況は大きな課題だと考えています。そのため当社では「まず徹底的にお客さまを知ること」をご提案しています。販売する相手を知らないことにはどんなビジネスも成り立たないからです。
まずは、お客さまの声を徹底して調べます。これまであらゆるところでヒアリングしたお声や、カスタマーセンターに寄せられたご意見なども分析します。最新のお声はウェブアンケートなどで簡単に集められます。それらの結果をロイヤル層、ライト層、離脱層というお客さま層ごとに分類して、それぞれの特徴を明確にします。この定量調査結果をもとに、次は各層ごとの定性調査を実施します。方法は層ごとのグループインタビューやデプスインタビュー(一対一の形式で深く聞く定性調査)です。
この定性調査で明らかにすることは、「お客さまのライフスタイル」から「美容知識のレベル」「そもそものニーズ」「なぜこの商品を購入したか」「購入に至る情報取得の方法」「商品の第一印象」「使用方法」「使用後の感想」「満足度の詳細」「他社品との比較」「価格評価」までです。
かなり詳細にわたってヒアリングするので、お客さまの傾向が明確になります。その結果を元に、どうやってお客さまをロイヤル層に引き上げるか、さまざまな施策を実行します。
◆お客さまの嗜好に合わせて
例えば、これらのお客さま調査でロイヤル層が「雑誌好き」という傾向が明確になった会社がありました。その理由は、その商品の新規獲得広告を、主に女性誌で展開していたことにあると推察できました。そこでお客さまに配布していた会員情報誌を女性誌のような構成に変えたところ、反応が出て記事に対する感想が寄せられるようになり、注文単価も徐々に上がっていきました。
また、新聞紙面で新規獲得している、あるメーカーのお客さま調査では、入口商品が「メーク下地」だったため、しっかりメークをするシニアのお客さまが多いことが分かりました。例えば、日舞の先生や、フラダンス会のメンバーなど、人前に出て発表会をするような活動的なお客さまが多かったわけです。
結果を踏まえて会報誌に、さまざまなシーンで役に立つメーク講座を掲載するようにしたところ、モデルとなるお客さまを募集した際の応募者も多く、大変な人気企画となりました。
◆お客さま目線で自社を斬る
このようにお客さまを徹底的に知り、その結果をさまざまな業務に取り入れると、これまで解決できなかった問題点が、次々と明るみに出て、解決の糸口が見つかります。
ある会社では、この徹底的なお客さま調査の後に、「では、自分たちもお客さま目線で、自社のNGポイントを探してみよう!」という社内活動を展開したところ、短期間に200ものダメ出しやNGポイントが課題として提出されたのです。
そして今、その200項目の課題は、各業務担当に割り振られ、解決策を探り始めたと聞いています。このように一つ一つ課題を解決していくことこそが、自社のノウハウになり、その積み重ねが、会社の実力になります。
◆他社と業界動向を分析する!
お客さまを詳しく知り、自社の弱点や問題点を解決すべく動き出せば、必ず会社は成長軌道に乗るはずです。
業務を改善する上で大切な取り組みをもう一つだけ付け加えるとすれば、他社の研究や、業界動向の情報収集でしょう。事業会社の方々に聞くと、業界内部に多くの人脈を持つ人は、勉強会や懇親会を通じて、情報交換を頻繁に行っているようですが、あまり交流のない人は他社情報が入りにくくなっているようです。
人脈が広いからと言って必ずしも業務に役立つわけではないでしょうが、業界動向には少し関心を持っても良いと思います。自社とは別の商材を扱っている企業や業界全体の傾向などを消費者目線で見ておくと、近視眼的な競合他社の情報などではなく、大きなビジネスの潮流が見えてくる場合もあり、そのような情報が次のアイデアを生み出すことにもつながるのだと思います。