一時の流行や割引では、お客様の心は動かなくなりました。今、必要なのは、数ではなく“熱量”のある顧客を育てること。商品やサービスの存在理由を見つめ直し、ブランドとしての「想い」をどう伝えていくか――。アフターコロナを生き抜く鍵は、そこにあります。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』1月21日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.68」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
共感と体験の積み重ねが、ファンを生む仕組みになる

今、店頭販売と比較すると通販は各社とも大きく売り上げを伸ばしているようですが、化粧品通販である当社はあまり伸びていません。マスク生活でメーク商品が全く伸びていないことが響いています。新規顧客獲得も動いていません。今、何をしておくべきでしょうか。
日本通信販売協会の売り上げデータを見ても、食品と生活雑貨の売り上げは前年よりも大きく伸びていますが、化粧品や衣料品の伸び率はそれほどではありません。ステイホームの時期が長くなっていますので、食材や家具などのニーズが高まるのは当然と言えます。しかし、化粧品や衣料品はアイテムによって売り上げの格差が激しく変動しています。
新規顧客獲得にかかるコストが高くなっている割に、人数を獲得できないので、投資金額を回収するためには、長い期間が必要になっています。その半面、競合が激しくなっており、初回割引のサービス競争が響き、離脱するお客さまも多く、LTVは低くなる一方と言えます。
新規顧客獲得がなかなかうまくいかなくなった理由は、あまりに新規参入企業が多くなり競合が激化したこと、もう一方ではECが通販のメインメディアになったため、ECの新規顧客獲得の価格が上がったことなどが挙げられます。
ECの初期の段階から新規顧客獲得に取り組んできた企業と比較して、メリットが少なくなってきていると言えるでしょう。コロナ禍の下でその影響は大きくなっていると思います。いわばビジネスモデルをもう一度見直す時期に来ているのかもしれません。
通販化粧品はまず新規顧客獲得が成功しないと、採算が取れる規模まで到達しません。しかし新規顧客獲得のみに傾注し過ぎると、獲得したお客さまが、安定的に継続購入してくれる時代はすでに終了してしまっているので、収益の悪いビジネスになってしまいます。要は、ビジネスの基本に立ち戻って、バランスの良い運営をしていかなければなりません。
コンセプトを磨き、価値を伝える――LTV向上の第一歩

新規顧客獲得がうまくいかないのであれば、既存のお客さまのLTVを上げる以外に方法はありません。そのためには、お客さまに購入メリットや使い続けることのベネフィットをきちんと訴求できる「コンセプト」を明確に打ち出していくべきです。
その商品の存在理由を明確にすることで、他社とは差別化された唯一無二のポイントを打ち出し、お客さまが実際に使用してその価値を認め、コンセプト通りの効果を実感し価値を認めてくれたら、「不要不急の商品」ではなく、そのお客さまにとっては、「必要欠くべからざる商品」になると思います。 多くのお客さまでなくても、ファンとか、熱心な信奉者、エバンジェリストのようなものと考えても良いでしょう。
今こそ、心を動かすブランド体験を積み上げるとき

要はファンとしての熱量がどれだけあるかということです。
そして今は、そのような中心顧客、核となるお客さまを一人でも多く育成しておくべきでしょう。そんな方々にマイブランドとして、他の商品には代えられないブランド価値を発信できれば求心力は高まると思います。
ファンになってもらうべき価値を生み出すためには、商品開発だけではなく感動を与えるようなサービス、気分を上げるアート的表現なども必要でしょう。商品のポジショニングやコンセプトを明確にすることで、より明確なメッセージが表現できるようになります。
また、コンセプトが明確になることで、業務に関わるスタッフの目標が一つになり、さまざまな業務にも磨きがかかることでしょう。それはどんなビジネスでも同じことです。関わるスタッフの熱量が成功をもたらすのです。
思わぬ感動や、熱い気持ちを伝えることによってお客さまに「想い」が伝わり、心の底から、「私の好きな商品」だと感じてもらえるようになります。そして本当にお客さまのお役に立ち、感謝されるブランドになれば「不要不急商品」から脱出できます。
コロナ禍の下でもやるべきことはたくさんあります。アフターコロナを見据えて、将来のブランド価値を高める活動をしておくことが、今最もやっておくべきことだと思います。

鯉渕登志子
フォー・レディーは、ブランドの存在理由を明確にし、お客様・商品・スタッフの想いをひとつに結ぶ戦略設計を行います。コンセプト開発からCRM施策、コミュニケーションデザインまでを一気通貫で支援し、ファンが育ち、企業が育つ“持続型ブランド経営”を実現します。







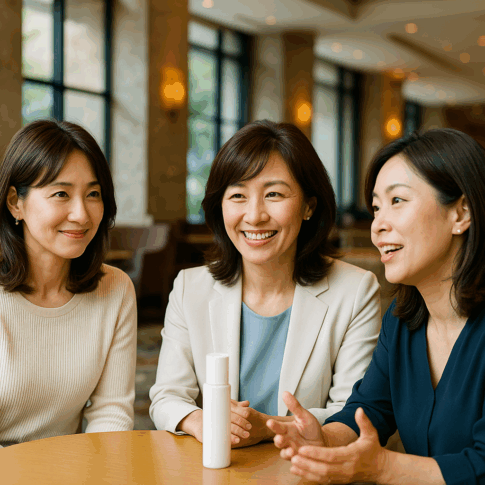









忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。