化粧品業界では、通販・店販・訪販といった業態の垣根がなくなりつつあります。競争が激化する中で、従来の「通販だから」の常識や手法にとらわれず、他業態の強みを学び、顧客視点で差別化を図ることが今こそ求められています。本コラムでは、通販化粧品企業が生き残るための視点と戦略について考察します。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』5月16日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.103」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
業態が違っても「化粧品を売る」ことは同じ。果敢にチャレンジを!

事業戦略マネジャー
昨年後半から新規獲得も効率が悪くなり、もともと良くなかった継続率も回復せず、客単価は少しずつ下がっている状態です。このまま通信販売を続けていけるのだろうかと不安になる時さえあります。
ご質問者の危機感は当然のことです。最近の通販化粧品を取り巻く環境は日々厳しくなっており、特に薬機法1や景品表示法2をきちんと守って、しっかりと顧客を育成しようとしている、いわば「正統派」の通販化粧品会社ほど苦戦しているようです。もちろん中には、安定した業績で、さらに今後の飛躍を計画している会社もあるので、一概に皆が危機感を募らせているというわけではないと思います。
しかし、昨年の後半から、新規獲得もリピート育成もうまくいっていない会社が多いのは事実。その理由としては、コロナ禍を経て多くの店販や訪販の会社が通販に参入したため、通販化粧品の市場自体は拡大したものの、既存の通販化粧品企業はレッドオーシャンの中であえいでいるようです。
「通販だから」という業態呪縛からの脱却を!

もちろんコロナ禍の前から課題があった会社、またその課題解決を先延ばししていた会社ほど、一気に問題が噴出してしまったというような印象で、特に中堅の老舗ほど苦戦しているようです。老舗はビジネスの手法が固定化している場合が多く、なかなか改善・改革が進まないという要因もあると思います。
では、この状況をどのように克服し、新しい未来をイメージすべきか?ということですが、私が提案したいのは、「通販で化粧品を売るという業態の呪縛から脱却すること」です。
通販だから直接対面しないとか、通販だからお届けは宅配とか、通販だから問い合わせはコールかネットのみとか、「通販だからこんなルールで」と自ら思い込んでいる「自主規制=通販業態の呪縛」から脱却することが、いま必要だと思います。
もちろん通販という業態に伴う法規制を守ったうえでの「呪縛からの脱却」です。
「店販」「訪販」など他業態の強み・弱みを知る!

その上で通販という業態の中の情報だけでなく、広く他業態の強みや弱みを研究するということが必要です。「化粧品を売る」という行為は全く同じなので、他業態は身近な競争相手なのです。
通販という「業態」が有利にお客さまを連れてきてくれるというのは、もはや過去の幻想です。すべての会社が通販に乗り出しているのですから、店販のタッチアップ3や美容部員のアドバイス、肌診断などをはじめ、訪販&サロン販売のパーソナル対応やお手入れ設備の充実など、学ぶべきことはたくさんあるはずです。
競合調査から「差別化」や「独自性」が生まれる

また同様に、同じ業態の中の競争相手ももっと研究するべきだと思います。
当社は得意先に、「競合会社のロイヤルユーザーになってください」とアドバイスをしています。ロイヤルユーザーとして商品を使用し、サービスを享受すれば、その会社の優れた点や弱点がよくわかります。競合の研究は、「お客さまになること」がもっとも手軽な方法なのです。
ところが、競合研究をお勧めすると、「まねをすることを勧められている」と勘違いをして、施策をまねするというようなことも出てきますが、「競合研究=まねすること」ではありません。競合を研究して、自分の戦略を見つけるための作業です。あくまでも自分の戦略は「オリジナル性」「他社との差異性」が大事なのです。
お客さまの喜びを最終目標に

どんなビジネスでも、最終消費者が熱量のある支持をしてくれている限り、規模の大小はともかくその方々に支えられて商売は成り立つものだと思います。そのためには、お客さまをしっかり見据えて、様々なサービスや情報提供を充実させていくことが不可欠だと思います。

鯉渕登志子
フォー・レディーでは、貴社の課題やお困りごとに寄り添いながら、新規獲得から顧客育成におけるマーケティングや企画開発、クリエイティブまでを一気通貫でご提案し、実務に即したトータルサポートをさせていただきます。









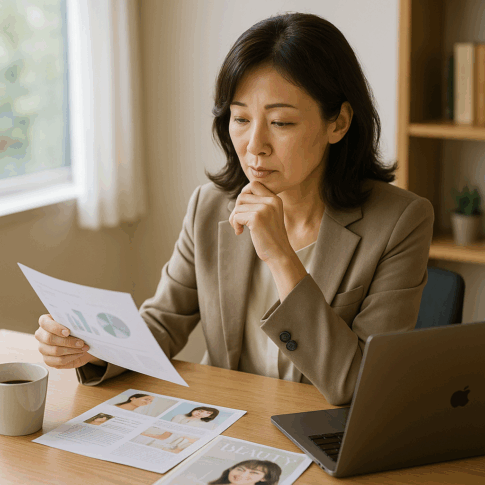







忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。