コールセンターの役割は単なる受注処理にとどまらず、企業とお客様をつなぐ重要な接点です。しかし実際には、オペレーターの育成やモチベーション維持に悩む声も少なくありません。「美容部員のような接客力を持つコールセンター」を実現するためには、何から始めればよいのでしょうか。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』12月14日・21日合併号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.44」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
窓口業務を超えて、お客様と企業をつなぐ「営業最前線」

コールセンターのオペレーターを「美容部員化」することが大事というのはよくわかっているのですが、何から始めていけばいいのか分かりません。またパートタイム社員など雇用形態の問題もあり、どのようにスタッフのモチベーションを上げていけばいいのかにも悩んでいます。コールセンターの人材を育てるにはどうすればいいのでしょうか?
弊社は通販化粧品会社の主に販売ツールを製作している広告制作会社ですが、時にはコールセンター用の教育マニュアルを作ることもあります。なぜマニュアル類の整備を担当するようになったかというと、いろいろ販売施策を考えてツール類を整備しても、受け皿であるコールセンターがうまく機能していないと、成果は上げられないということに気がついたからです。
それ以降、さまざまなコールセンターを見学させていただき、お話を聞いて思うのは、インハウスでも、外注でも、コールセンターはお客さまと直接ふれあう貴重な場であるということ。かかわるスタッフ全員がその商品の「営業最前線1」という意識を持って、取り組むためのソフト力の整備が必要だということです。
まずはスーパーバイザーをはじめ、スタッフに「営業最前線」の役割を担っているということをしっかり伝えましょう。そのためには、会社の経営方針(コンセプト)からコールセンターの役割(ポジションやミッション)、現状の課題や今後目指すべき理想のセンター像、組織体制と職務定義、社内の各部門との情報伝達連携の方法、人材育成の仕組み、業務内容の詳細などを記載した業務マニュアルを整備することから始めてはいかがでしょうか。
作業内容を早く覚えてもらうことも大切ですが、そもそもどんなスタッフになって欲しいのか、会社の期待やその役割を認識しないと、よい接客はできないはずです。コールセンターのマニュアルは、会社の「接客ルール」の基本なのです。明文化して新入社員もすぐに理解できるようにするべきです。
その上でロールプレイング2を重ねて、全社的に教育していくことが大切です。
成功するコールセンターは責任者とスタッフの関わりが濃密

成功しているコールセンターは、責任者とスタッフの関わり方がとても濃密です。
仮に外注のコールセンターだとしても、本社の人間が毎日訪問するなど、本気で「営業最前線」に関わっていこうという意思が伝わってきます。また、コールセンターから収集するデータもお客さまの声を事細かに分析して、商品開発やサービス内容の見直しに役立てています。
うまく機能していないコールセンターは、受注本数など大ざっぱなデータしか集めていないことが多く、それではお客様の声を拾い損ねてしまうでしょう。「営業最前線」として大事に考え、責任者が本気で関わろうとすれば、それは社内でも、外注先でも必ずスタッフに伝わります。
たとえ雇用形態の異なるパートスタッフであっても、モチベーションをアップさせる要因はいろいろあるものです。顧客育成がしっかりしている会社はお客さまの質がいいので、心地よいコールが多く、オペレーターも「すすんで電話を取りたくなる」ようです。そのような前向きの姿勢は、声に必ず表れるので、お客さまも心地よい会話ができるはずです。
自社商品愛用と会話品質評価が“おもてなし応対”を生む

コールセンタースタッフ全員とビジョン(役割やポジション、将来構想など)を共有できれば、コールセンターの「美容部員化」は達成されますし、人材が自動的に育っていく環境にすることも可能なはずです。
また、できればオペレーターさんたちには、自社商品を愛用して欲しいですし、会社は人材を育てるためには受けた電話の本数だけではなく、会話内容の品質も評価できるような仕組みを検討してほしいものです。
そうすれば「営業最前線」として「おもてなしのある応対3」が可能になると思います。

鯉渕登志子
フォー・レディーでは、コール対応調査や「美容部員化」を目指した教育研修の実績もございます。単なるマニュアル整備にとどまらず、現場に寄り添いながらスタッフ一人ひとりの接客力を育てることにおいて、ぜひ私たちにご相談ください。
用語解説
- 営業最前線-お客様と最初に接点を持つ場所を指す言葉。通販会社におけるコールセンターは、単なる受注窓口ではなく、お客様の声を直接受け止め、会社の姿勢を伝える「営業活動の最前線」として位置づけられる。 ↩︎
- ロールプレイング-実際の電話対応を想定し、オペレーター同士または上司と練習する教育手法。会話の流れを体験的に学ぶことで、状況に応じた応対力を高めることができる。 ↩︎
- おもてなし応対-単にマニュアル通りの処理を行うのではなく、お客様の気持ちに寄り添い、心地よい会話を提供する姿勢。信頼関係を築き、ブランド価値を高める要素となる。 ↩︎







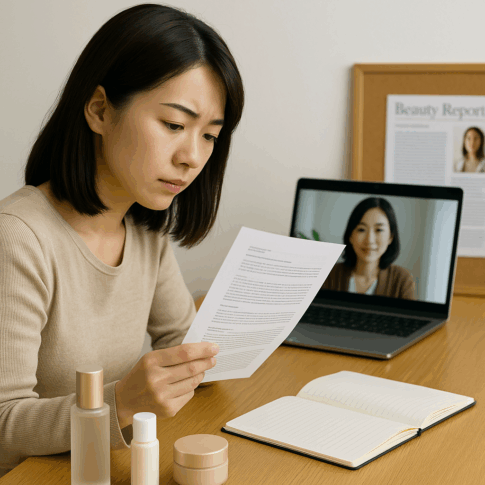

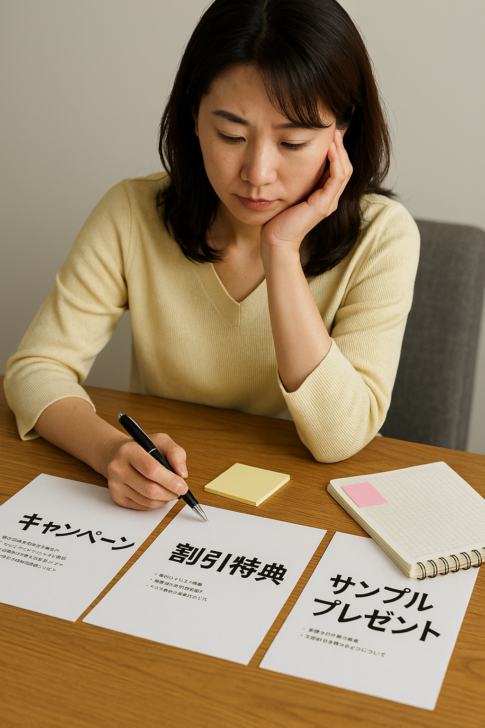







忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。