コロナ禍で急速にデジタル化が進み、通販事業は多くの企業が「安定した販路」として成果を上げてきました。しかし、社会が徐々に日常を取り戻し始めた今、「次の一手」を考える時期が来ています。アフターコロナの時代に向けて、今から準備しておきたい視点を探ります。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』6月17日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.73」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
「また会いたい」を形にする。お客様と一緒にブランドを育てる時代へ

弊社は通信販売で化粧品を販売していますが、店頭販売の人たちに比べれば、コロナ禍の影響をあまり受けなかったと思っています。しかし世の中が落ち着いてきたら、何をすべきか、今から準備しておくことを考えたいです。
全国的にはまだまだ予断を許さない新型コロナウイルスの感染状況ですが、すでにワクチン接種を受けた高齢者から、徐々に明るい話題が聞こえてきました。例えば、接種を終えた人は「ほっとした」「やっと孫に会える」「安心して出かけられる」などなど。
私の身の回りでも、自宅に引きこもり状態だったシニア層の女性たちから、「コロナ禍が収束したら、旅行や会食に行きたい」「都会に遊びに行きたい」と計画を話す人が多くなってきました。それだけこの1年半の自粛生活が、自由を奪われた我慢の時期だったということなのでしょう。
弊社でもお得意先と相談して、緊急事態宣言発令中はすべてのお客さまイベントを中止していましたが、それ以外の時期に感染予防対策を徹底して行ったミニイベント(お客さま撮影会、お客さまインタビュー、ミニミニ座談会)は、大変喜ばれました。
お客さまからは「まったくどこにも出かけられなくて、気分が滅入ってしまうほどだったので、外出する理由ができて良かった」「久しぶりに外出してフルメークのレッスンもできてうれしい」など、我慢生活の中で、小さな楽しみを見つけられたことへの感謝の言葉をたくさんいただきました。
心なしか、会員情報誌で企画したお客さまアンケートや抽選プレゼントなどの応募数も多くなっているような気がします。つまり人々の我慢生活が限界に近づき、開放感を待ち望んでいることが、ひしひしと感じられるようになってきました。
リアルでも、オンラインでも。「参加型企画」でお客様と交流を

そこでコロナ収束後を予測してみると、前述したような気分のお客さまに「小さな楽しみを提供」することが喜ばれるのではないかと思います。つまり、自粛期間中はなかなか実現できなかった「人と人とのつながり」を取り戻すことです。そのためには、通販化粧品の場合は「お客さま参加型企画」を多くすることが、とても有効なのではないかと思います。
「参加型」といってもいろいろな方法があります。対面で行うことでは、セミナーやお手入れ会、お客さま座談会、インタビュー会、体験撮影会、美容相談会などです。もちろんコロナ収束後に行う場合でも、感染対策を完璧にしておくべきことは言うまでもありません。自粛我慢生活が収束したら、このような「お楽しみの機会」を演出してあげることも、お客さまとの絆を深めるよい機会になると思います。
もちろん直接対面しなくても、定着したウェブ活用のイベントでも喜ばれることでしょう。ウェブセミナーは全国区で行えますし、一対一のカウンセリングも可能な時代になってきました。つまりウェブでも店頭販売並みの接客が可能な時代になってきたのです。
ウェブが苦手な世代でも、お手紙やお電話でのやり取りで、アンケートやインタビューへの参加は可能です。「お客さま参加型」の良いところは、何らかの企画に参加した方は多くの場合、ブランドの好感度が高くなり、LTVも高くなる傾向があります。参加型はお客さまとの絆を深めるために不可欠の方法です。
集めた声は必ず“お返し”を──参加の手応えが信頼を育てる

ただし、運営上注意していただきたいポイントがあります。寄せられたご意見やお客さまアンケートの回答は、集めるだけでなく、必ずまとめたレポートなどで結果をお知らせしましょう。アンケートを取っただけで、結果をお知らせしないのは、回答しているお客さまの視点で考えると「自分の意見がどのように活用されたか分からない」という疑問が生まれ、不信感の要因になります。お客さまのアンケートは、丁寧に集計して結果を公表し、どれだけ改善の役に立ったかをお知らせするべきです。
「お客さま参加型」はお客さまとブランドの距離を縮め、絆を強くすることができます。ブランド側も単にお客さまの年代や肌悩みだけではなく、その価値観やライフスタイルを想像できるようになり、商品や販促物、会報誌のコンテンツなどのものづくりやコミュニケーションツールの内容に大いに役立つことでしょう。
コロナ禍が収束して、日常生活が戻ってきたら、さまざまなチャンスを捉えて、「お客さま参加型」でお客さまとともに作るブラントにしたいものです。

鯉渕登志子
アフターコロナの時代は、企業とお客様の関係を改めて見つめ直す絶好のチャンスです。これまで制限されていた“つながり”を取り戻し、リアルでもデジタルでも、お客様の声が生きる企画を生み出していくことが大切だと思います。フォー・レディーは、そんなお客様との絆を育て、共感が循環するブランドづくりをこれからもお手伝いしてまいります。






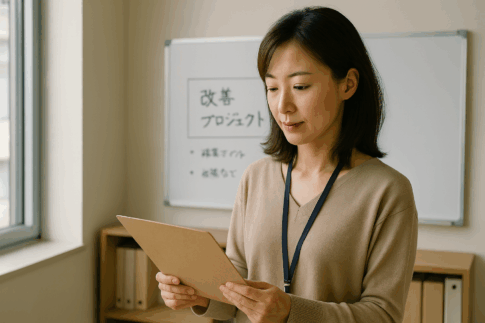










忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。