コロナ禍をきっかけに、あらゆる世代でスマホ利用が一気に広がりました。とはいえ、60代以上のお客さまの使い方は若い世代とは大きく異なります。通販化粧品企業がこの層に向けてスマホ活用を進めるには、どのような点から取り組むべきでしょうか。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』6月25日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.64」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
シニア世代にはデジタル完結ではなく、リアル媒体との併用を
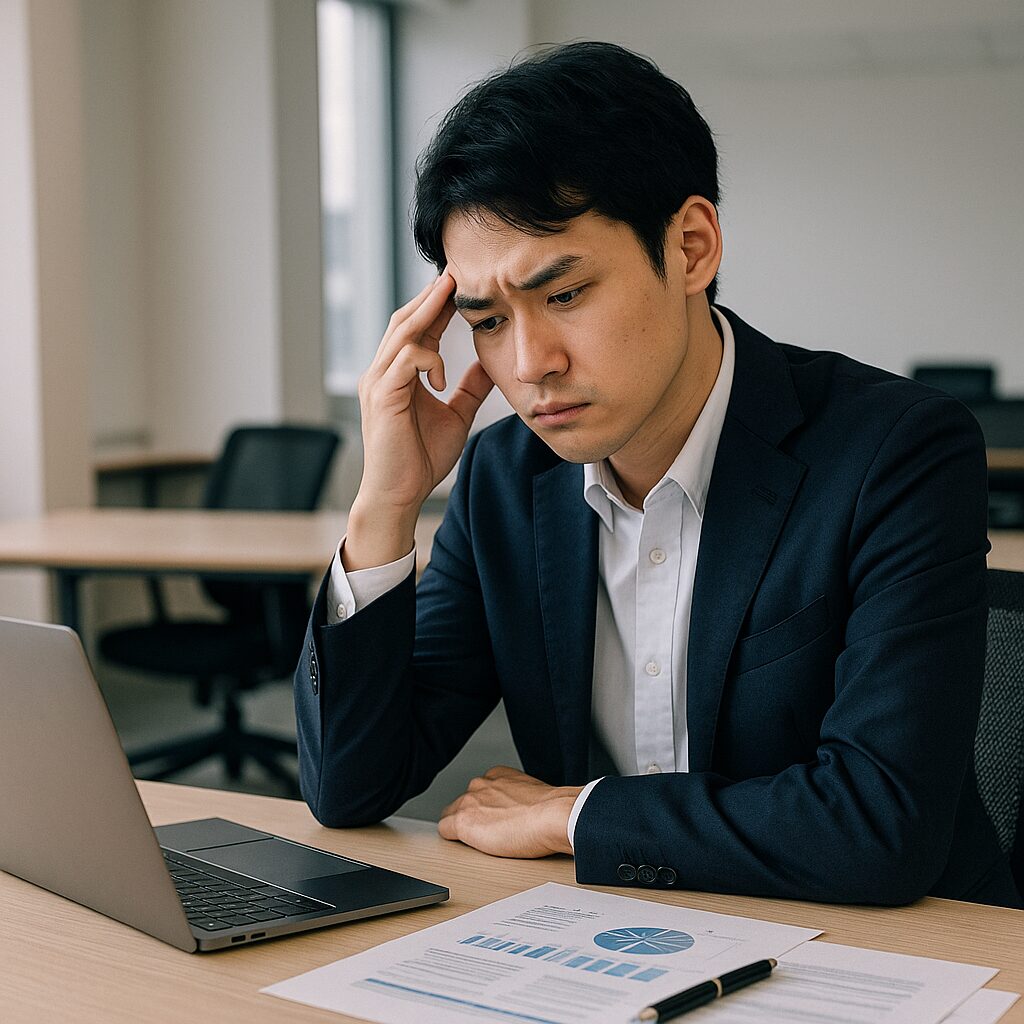
コロナ禍を経て世の中はすべてデジタル化しそうですが、弊社のお客さまは60代以上の女性が多く、これまでウェブのコミュニケーションは手薄でした。しかしこの状況下では、もっとスマホ活用を進めなければならないと思っています。何から取り組めばよいか、どんなことに留意すればよいか、アドバイスをお願いします。
60代のスマホ利用率は46.4%(総務省「平成30年通信利用動向調査」)となり、伸び率も他の世代より高いといわれています。しかもこのコロナ禍にあって、利用率は一気に高くなっていると考えられます。
とはいえ、お客さまにグループインタビューでお伺いすると、決して若い世代のようにデジタル端末を使いこなしている人ばかりでないことが分かります。
確かに最近、中高年のお客さまはほとんどスマホを持ち、主な使い道は「ネット検索」と、「LINEアプリ」を利用した家族や友人との連絡が中心です。さらに、年代が高くなるほど、検索すらあまり利用している様子はなく、テレビや新聞など従来型のマスメディアから情報収集している様子がうかがえます。
ネット通販の利用率は高まっていますが「注文はスマホよりパソコン」という意見が多く、その理由として「スマホの画面は小さく見にくいので、もっと大きいパソコンの画面で確認したい」「パソコンにクレジットカードの情報を入れるのが不安」などの意見が聞かれました。
スマホからもQRコードを読み込んで注文する人もいましたが、決済は代引きやコンビニ払いなど、年代ならではの行動パターンが見えてきます。コロナ禍で、多少は必要に迫られて利用率は上がったとしても、急に若い人と同じようにスマホを使いこなしているとは思えません。
また、SNSについては、多くが日常の連絡用にLINEを使用しているものの、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムについては、「ごくたまに」や「利用しない」という声が圧倒的です。フェイスブックで知り合いの近況を見ることはあっても、見ず知らずの人とネット上で「つながる」「共有する」という意識は希薄であることが分かります。
このような現状を考えると、今のシニアに沿ったデジタルコンテンツの在り方が見えてくるのではないでしょうか。
身近なLINE、シニアとの距離を縮める第一歩に

スマホを活用する施策を考えるなら、まずLINEアプリを中心に考えるとよいでしょう。独自のアプリを開発するより低コストですし、何よりシニア層が使い慣れているのは最大のメリットです。
公式アカウントを開設したら、まずは友達追加をしてもらいますが、この状態でメッセージを一斉配信しても、効果はあまり得られません。最も重要なことは、お客さまに会員情報を登録していただき、自社の顧客番号とLINEアカウントをひも付けることです。これによりLINEアカウントの友達が、顧客データベース上のどの会員なのか判別できるようになり、パーソナルな配信ができるようになります。
最初はDMや会報誌を「発送しました」という予告メッセージから始めてもよいでしょう。キャンペーン内容や新製品情報などを簡潔に紹介し、「ぜひご覧ください」と伝えることで、開封率のアップが見込めます。
つまりシニアとのコミュニケーションは、まだまだデジタル情報だけのやり取りでは完結せず、紙媒体などの従来型メディアを融合させた施策が有効です。
お客さまはスマホで情報を受け取り、紙媒体で確認して納得するというプロセスを踏むことで、安心して注文することができるのではないでしょうか。紙媒体からデジタルに移行するのではなく、車の両輪のように機能させていくことが成功の鍵となるでしょう。
手応えを感じてきたら、目で楽しめるようなリンク付きの画像を配信したり、使い方をおさらいするための動画コンテンツに誘導したりするのも有効です。自社のオリジナルキャラクターが友達のようにフレンドリーな口調で案内するというのも、お客さまとの距離を縮める効果があるかもしれません。
ストレスのない画面設計と、安心できる確認表示を

今のシニアは若々しい気持ちにあふれていますが、それでも視力や手先の衰えは進みます。LINE上はもちろんリンク先でもお客さまがストレスなく見ることができるよう、文字やボタンのサイズを大きくする、視認性のよい配置、配色にするといった工夫も必要です。
中でも注文ミスは大きなトラブルになりかねません。確認メッセージは、商品、数量、価格など、細部まで分かりやすく表示する必要があるでしょう。

鯉渕登志子
シニアの気持ちや行動を理解することは、ブランドのファンを育てる第一歩です。フォー・レディーはその理解を基盤に、施策設計からコンテンツ制作まで一貫してお手伝いします。





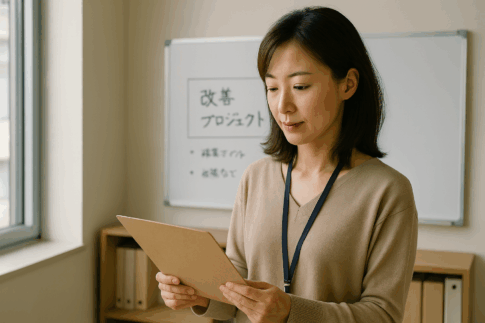











忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。