急成長を遂げた通販化粧品業界。しかし業務全体を見渡し、新しい挑戦を推進できる中堅人材の育成が追いついていないという声が多く聞かれます。通販化粧品業界に特有の人材育成の難しさをひも解きつつ、今後取り組むべき育成施策やマニュアル整備の方向性について解説します。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』2月21日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.10」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
現場をつなぎ、挑戦を推進する“中堅層”が育たない理由

なかなか通販化粧品のプロと呼べる人材が育ちません。当社は急成長した中堅規模の通販化粧品会社です。それぞれ自分が担当している仕事はある程度こなせるのですが、社内の業務全体を見渡して、ディレクション1できる中堅の人材が少なく、新しいことへのチャレンジも滞りがちです。
通販化粧品だけでなく、今あらゆる業界で「人材育成」が問題になっていると思います。特に中堅以下の若い世代を育てることが大変難しくなっています。中でも通販業界は、業界としては伸びているものの、人材を育てる環境が整っていないのではないかと思います。
その主な理由としては、通販は意思決定をする超ワンマンが存在すれば、その他の人は各部門に分かれたパーツの仕事をしていても、とりあえず成り立つビジネスだったからだと思います。店舗販売の場合は店長を育成しなければならず、訪問販売は一人一人がプロでなければ成立しない業種です。しかし通販の場合、カリスマ経営者が意思決定すれば、とりあえずは回っていくビジネス構造。これが最近まで続いていたと言えるのではないでしょうか。
まして業界として歴史が浅いだけに、通販化粧品に特化した人材育成のシステムが、なかなか整備されていないのが現状ではないでしょうか。
その反面、通販ビジネスが好調なだけに新しくチャレンジしなければならない業務メニューが目白押しです。つまり業務のスピードに人材育成が追い付いていない状況なのではないかと思います。
「通販」と「化粧品販売」両面の理解が必要
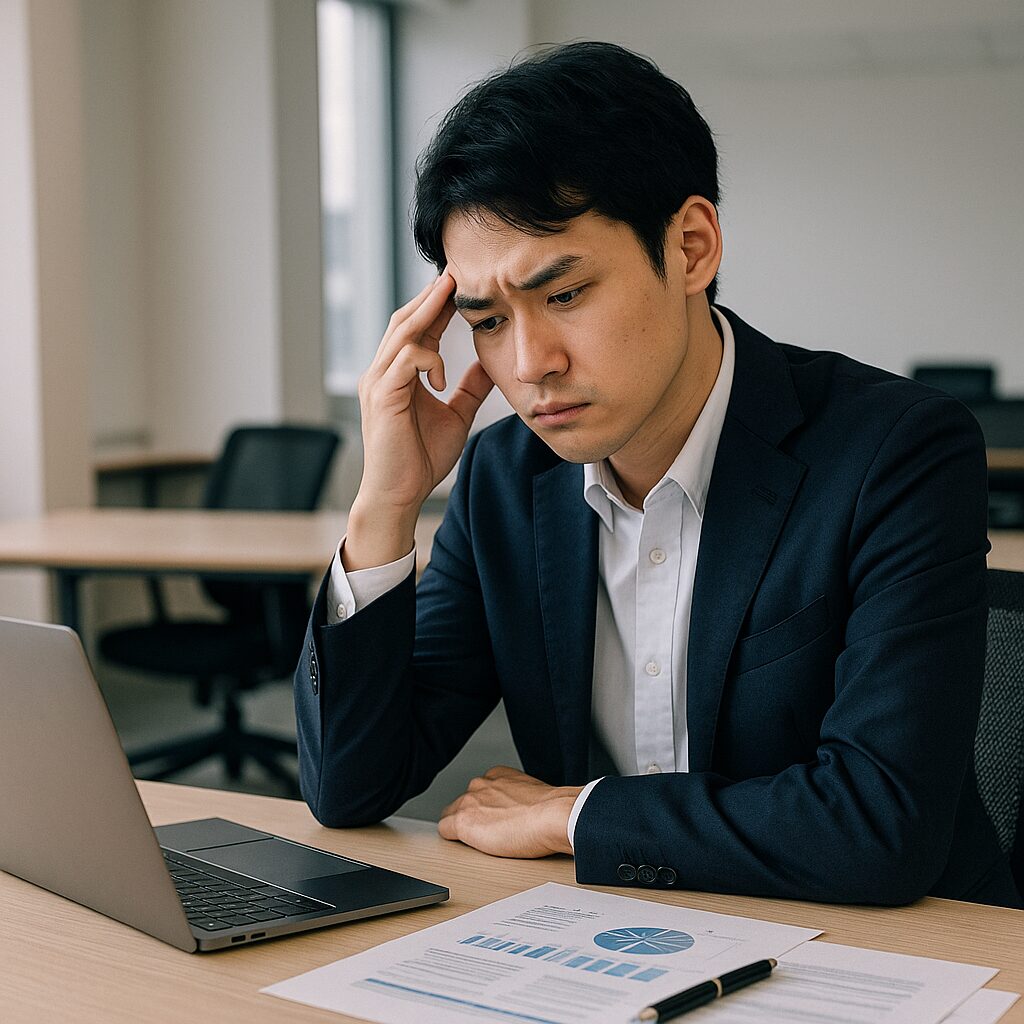
通販化粧品の人材育成は、「通販という販売システム」と「化粧品を売る」という商売の両方を教える必要があります。そして、この両面を教えることで、通販化粧品ならではの「商売のセオリー」が見えてきます。
私はまずこの「セオリー」を教えないと、単に各部門のパーツ仕事を教えていてもなかなかディレクターのような存在の人材は育たないと思います。
次に、独自の美容についての考え方やコンセプトの「自社の美容理論2」を教えなくてはなりません(これは、どこのメーカーでも備えておくべきものです)。
次に自社の商品についての徹底的な研究と、同時に他社研究を徹底させなくてはなりません。
また、最も通販的な業務として、ビジネスを数値でとらえるという、「販売データの分析方法」を学んでもらう必要があります。そして、さらに統計のビジネスらしく、検証結果を数値で読み、次に修正していくというPDCAサイクルを回すことも教えなくてはなりません。

社内の共通言語「マニュアル整備」が育成の第一歩

このように通販ならではの人材育成の項目は、主要項目だけでも多岐にわたります。したがって少しでも理解を早めるために、各項目の「マニュアル類」を整備する事をお勧めします。
意外に大きなビジネスをしている会社でも、「教育マニュアル」が充実していなかったり、あったとしても現実の業務や作業にはすぐに応用できない抽象的なものであることが多いような気がします。これでは、体制ができていないのに、「勝手に育て」と言っているようなものです。
通販化粧品ならではの教育ツールやマニュアル類を整備して、新人たち、あるいは他業界からの転職の方々に、短期間にこの業界で活躍していただけるような「人材育成」を行ってほしいものです。

鯉渕登志子
フォー・レディーでは、美容マニュアルはもちろん、コールセンタースタッフへの教育なども行った実績がございます。社員教育においてどのような課題があるか、まずはご相談ください。







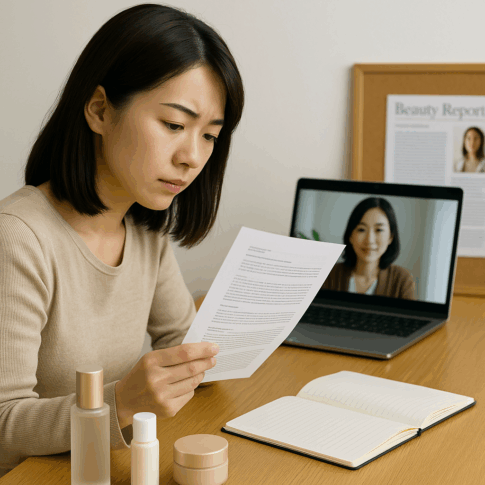


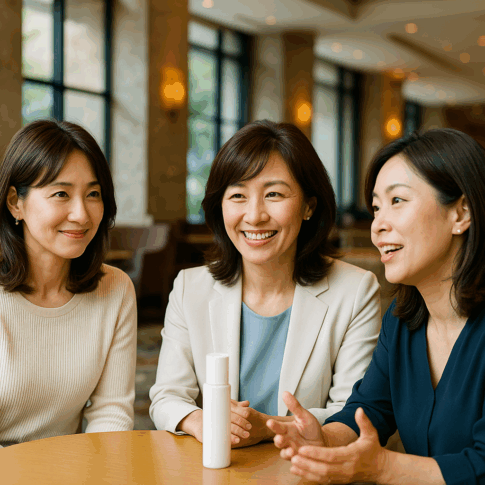






忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。