これまで通販は、メーカーが自らお客さまとつながれる「特別な販売ルート」でした。ところが、店頭販売がEC化を進め、消費者の購買行動が変化した今、両者の垣根は急速に薄れています。通販企業は、これからどのように販売チャネルを再構築すべきなのでしょうか。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』5月13日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.72」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
「通販か店販か」ではなく、両輪でブランドを育てる時代に

数年前から店頭販売にも進出しています。今後、通信販売と店頭販売のどちらに注力すべきか迷っています。販売チャネルに応じて担当部門を分けているのですが、ときどき主張がかみ合いません。通販と店販の両方をうまく運営していくためのこつも教えてください。
直接販売する自社通販と卸が中心となる店頭販売との担当部署間の争いは、かつてはよく耳にしたのですが、いまだにうまくコントロールできていない会社も多いようです。
同一商品だと、通販部門で行う施策が卸先の小売店からクレームになることが多いからでしょう。通販化粧品会社が一度は通る道といえます。両方をうまくコントロールして拡大してきた会社は、同一商品であっても通販部門では「単品値引きはしない」「同時期の通販特典は店舗でも行う」など、さまざまな工夫をして運営してきたはずです。そこには全社としての大きな戦略が貫かれているからです。
つまり、「通販で買っていただいても、店頭で買っていただいても、どちらもわが社のブランドのファン」という考え方です。ブランドの認知率が高くなれば、通販でも、店販でも、どこでも買えるのが利便性の高い「ブランド」ということになります。収益や施策の差などから社内で対立していても、お客さまにとっては同じブランド。そこに不協和音を感じたら、せっかくのファンの熱が冷めてしまうのではないでしょうか。
通販と店販の融合が、ブランドを次のステージへ導く

ネットによる検索と通販が融合したことによる購入の利便性が高まり、コロナ禍という環境要因も加わって、今、小売業はかつてないスピードで大きく変化しています。リアル店舗を生かした通販的な運営をスタートさせ、過去の「通販」と「店販」の役割と機能が変化し、進化してきているのです。
店舗の対面販売はショールーム化し、通販と店舗はシェアを取り合う関係ではなく、融合してマーケットを育てる関係になりつつあります。通販VS店販と区分すること自体が、今ではナンセンスになり、両方の機能を兼ね備えることは小売業の常識になりました。
しかし、店舗から通販への参入はこの流れをうまく利用できているように見えますが、通販会社が本格的に店販へ参入しているのは、中堅以上の会社に限られているようです。
通販からスタートした会社が、店舗に参入するのは、まだまだ大きな壁があるようです。理由としては「卸価格になるので利幅が薄い」「名簿が取れないので直販がいい」といったところでしょうか。そして、この自粛ムードの中で直営店舗を出店するのは、誰でも二の足を踏むでしょう。
しかしショールームを持つと考えれば、今こそ出店のチャンスではないでしょうか。これだけ急激にEC化が進んでも、コロナ禍が終息すれば、消費者はリアル店舗での買い物も楽しむはずです。そのときを見越して、どのルートでも買える「ブランド」になる足掛かりを作っておくべきです。
本来あるべき姿は、個性がしっかりと確立されてブランド力がある会社は、自社サイトでも買えて、卸でも値引きされずに、アマゾン、楽天、百貨店、バラエティーストアなど、どこでも買える状況を作ることです。
お客さま目線で、通販と店舗をつなぐ時代へ

小売業がサービスの一環として通販をスタートさせているため、「通販だからこそ」のメリットは、今後少なくなると予測されます。それに対抗していくためには、通販も「店販」を充実させることが不可欠なのではないでしょうか。
小売業はお客さまの購買行動の変化についていかなければ生き延びることはできません。これまでは商流の規制などでメーカー通販はなかなか店販に進出し難いことも多かったようですが、コロナという情勢から「どこでも買える」体制を作る会社が増えてきています。通販化粧品会社も、ファンであるお客さまのためにアクセスルートを多く作る必要があります。
そのためには、「通販」と「店舗」がどういった協力をするべきかを考え、その体制を早く整える必要があると言えます。できれば、お互いのルートを利用し合うくらいでなくてはならないと思います。理想的には、通販と店舗で顧客名簿を統合し、お互いを誘導し合うことで、相乗効果を出すことですが、そこには業態ごとの商流1という大きな壁が立ちはだかるので、それを打ち破る新しい仕組みを構築したいものです。
市場環境が大きく変わっても、徹底したお客さま目線を社員一人一人が持ち続けていれば、会社が生き延びるポイントが見えてきます。販売ルートの整備についても、自分の購買行動を思い起こせば、おのずと戦略のヒントが見えてくるのではないでしょうか。

鯉渕登志子
通販と店販の垣根を越え、「どこで買っても、同じ想いが届くブランド」へ。フォー・レディーは、お客様の声に寄り添いながら、ブランド全体でファンを育てる仕組みづくりをお手伝いします。
用語解説
- 商流(しょうりゅう)-メーカーから消費者までの流通経路。卸業者、小売業者など、販売に関わる取引の流れを指す。業態によって商流が異なるため、データ共有や価格設定が課題になることが多い。 ↩︎



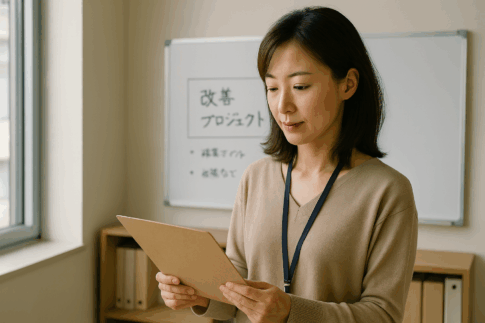




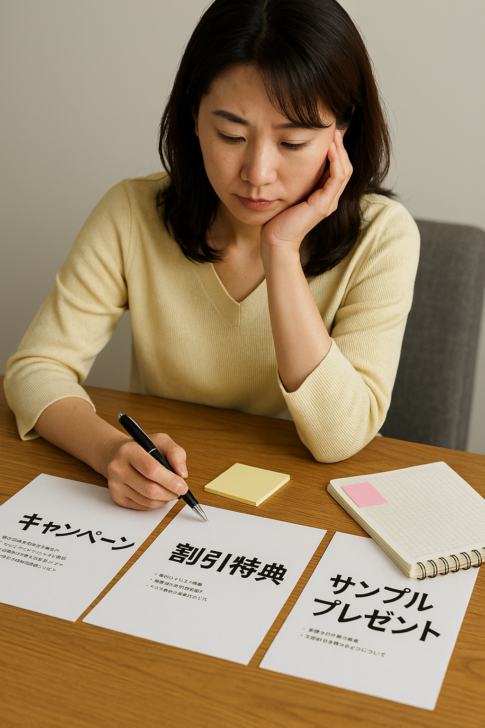








忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。