看板商品の売上が伸び悩み、次の一手が見えにくくなっている――。そんな悩みを抱える通販化粧品企業は少なくありません。その背景のひとつに、“他社との差”が見えにくくなった同質化の問題があります。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』8月3日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.94」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
「売れる仕組み」より「良い商品」づくりがブランドを育てる

看板商品の売り上げに陰りが見えてきました。新規獲得、引き上げ施策や顧客育成もしっかりやっているつもりです。しかし競合商品も多くなってきており、今後より改善すべき点や不足している点をどのように修正していけばいいでしょうか?
先日、老舗化粧品専門店の経営者たちの座談会記事を読み、考えさせられることが多くありました。
ちょうど100年前に資生堂が設立した「チェインストア制度1」は、値引き競争が激化して苦境に立たされていた小売店や問屋、メーカーが共存共栄できるよう定価販売を推進するボランタリーチェーン契約を結び繁栄したということです。
その後、化粧品販売に限らず戦後の多くのチェーン店は、より効率よく効果的に大量の商品を売るためのマーチャンダイジングのビジネスモデルを採用し、同じ商品設計や成長戦略を実施したことで多くの店舗の”同質化”を招いたようです。
前述の化粧品専門店オーナーいわく、「今は同質化とは対極の、お客さまが面白いと思うセレクト性が一段と求められている」。
「売れること」ばかりを追わずに。通販にも“良い店”づくりの発想を

お客さまを楽しませる店づくりという点で、化粧品専門店の今後は、「接客を含めたあらゆる部分で高級路線を進めることにあるのではないか」とおっしゃっています。
ところが、服や時計といった専門店に比べて高級化粧品が出遅れた背景には、「良い店づくりよりも”売れる店”づくりが評価され、求められ続けたことにある」と主張しています。
「業界全体が、売れる店づくりではなく”良い店”づくりを評価する意識改革をしなければ、化粧品専門店らしさを発揮した冒険はしにくく、存在意義を高められない」と危機感を募らせているのが印象に残りました。
これは、まさに今の化粧品通販ビジネスにおいても、まったく同じことがいえるのではないでしょうか。いやむしろ、店を持たない通販のほうがもっと深刻かもしれません。
価格訴求ばかりに偏るといずれ多くの離脱客を招くことはよく知られていることですが、かといって一方的にブランド価値ばかりを訴求していても新規獲得するのは難しい状況です。要はブランドのコンセプトと販売促進のバランスなのです。
お客さまとのコミュニケーションツールであるDMやメルマガ、会報誌などが、売るためのカタログと化していないでしょうか? 常に、お客さまに新しい気づきやワクワク感、役に立つコンテンツなど、楽しみを届けているでしょうか?
今一度、自分たちのビジネススタイルや販促プロモーション、お客さまとのコミュニケーションを見直す必要があるのではないでしょうか?
差が見えにくい時代にこそ、“誰のために”を問い直す
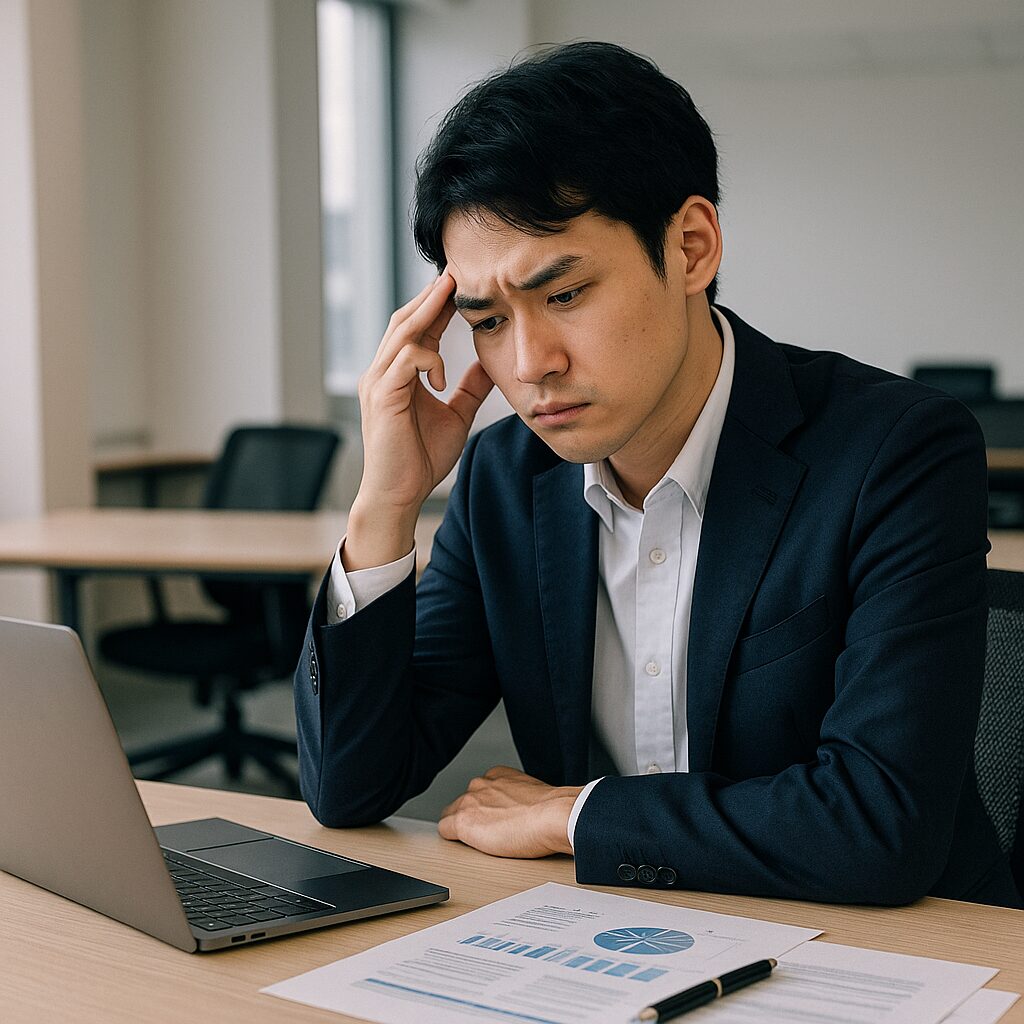
通販化粧品のマーケットに存在する多くのブランドが、お客さまに差異が分からないほど同質化してしまっては、お客さまを楽しませることなど、できるはずがありません。
大量の広告宣伝で「売れる商品」と、お客さまにとって真に「良い商品」が、必ずしもイコールではないということは、老舗専門店のオーナーたちの発言を待つまでもないことです。
売り上げのみを目標にしたための同質化やこだわりのないモノづくり、お客さまの気持ちに寄り添わない販売戦略を続けていると、やがてはお客さまの期待を裏切ることになり、通販化粧品というマーケットそのものの存在価値を危うくしてしまいます。
それを回避するためには、常にわずかでもアップデートと、小さな工夫を積み重ねることこそが、お客さまに面白いと思ってもらえる商品づくりだと思います。またコミュニケーションや情報発信は、お客さまに必要とされるコトやモノを、一人一人に寄り添いながら続けていく必要があると思います。
そうして企業やブランド同士が創意工夫をすることで業界内に競争力が生まれ、マーケットの活性化につながっていくと思います。
そのためには、「自分たちのお客さまは誰か?」の基本に立ち返って真摯に取り組むことです。そのお客さまたちのために自分たちは何ができるのか? どうやったら喜んでもらえるのか? そんなことを常に自問自答することが大切なのだと思います。
そうしなければ、これからの通販化粧品ビジネスは衰退する一方になってしまいます。新規獲得が上手くいかない今だからこそじっくり腰を据えて将来のことを考える必要があると思います。

鯉渕登志子
「売れる仕組み」より、“選ばれる理由”をつくる。私たちは、数字の裏にあるお客さまの気持ちを見つめ、共感と信頼でブランドの価値を育てていきます。フォー・レディーは、お客さま起点のブランドづくりを支援します。
用語解説
- チェインストア制度-1920年代に資生堂が導入した仕組みで、メーカーと販売店が協力して定価販売を守り、共存共栄を目指した小売支援制度。 ↩︎

















忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。