お客さまの美容への意識や関心が高まるいま、ブランドに求められるのは「私の肌に何をしてくれるのか?」という、よりパーソナルに向けた効果や情報です。そこで需要が高まっているのが、一人ひとりの顧客に寄り添う美容相談サービス。通販でありながら、店販に匹敵するような丁寧できめ細かい仕組みづくりが業界で生き残るための鍵といえます。今回のコラムは、『日本流通産業新聞』11月2日号に掲載された「強い通販化粧品会社になるために 基礎講座Q&A vol.97」です。ぜひご覧ください。

日本流通産業新聞
通販・ネットビジネス・健康食品・美容業界などの最新動向を専門的に取り上げる業界紙です。実務に直結する情報を多角的に発信し、多くのビジネス関係者に支持されています。
「届ける」だけじゃない!店販に匹敵する上質な通販サービスを

新規顧客の獲得コストが膨大となり苦戦中です。メイク品の売り上げはコロナ禍より若干回復傾向にあるとはいえ、そのうちスキンケアも含めた全商品の値上げに踏み切るしかなさそうです。お客さまにご満足いただくためには、新価格に合ったサービスとして美容相談を考えていますが、果たして通販でどこまで可能なのか見当がつきません。
最近お客さま調査をしていて実感するのは、お客さまの美容知識が以前よりとても高くなっているということです。
なかでも美容成分に関する認知レベルが顕著です。5年ぐらい前まではヒアルロン酸やコラーゲン、セラミドなどよく聞く有名な成分名は挙がっていました。しかし今日ではレチノールやアスタキサンチン、フラーレン、ナイアシンアミド、ヒト幹細胞培養液といった成分名が当たり前のようにお客さまの会話の中に飛び交っており、しばしばこちら側が圧倒されてしまうようなこともあります。
美容成分に関するアンケート調査結果でも、化粧品を購入する際に「配合美容成分をみているか」や「配合成分を重視するか」という問いに対し、いずれも8割弱の人がYESと回答しています。コロナ禍を機に、お客さまは自分で検索して情報を取得するという方向に大きく変化したことを認識する必要があります。
また、店販と通販の境界線が曖昧になってマルチチャネル化が進み、お客さまは通販であれ、店販であれ「私にとってどうなのか?」というよりパーソナルなニーズを満たしてくれる商品を見極める知識を持ち始めたということです。
“なんとなく”では売れない!手強い顧客にどう応えるか

お客さまの美容に対する関心や知識や要求が高くなることは、たいへん喜ばしいことには違いありません。と同時に、これまでのようにエモーショナルな雰囲気に任せて”なんとなく”化粧品が売れていた時代は終わったとも言えるのではないでしょうか。
どんな美容成分が配合されていて、「私の肌をどう良くしてくれるのか」が問われる手強いお客さまを相手に、どう応えていくのか—。それが化粧品会社に突き付けられている課題だと考えられます。
薬機法に抵触せずに、顧客を納得させられるだけのエビデンスの開示や方法を見つけなければならないですし、不特定多数を対象にした従来の通販広告だけでは「私の肌をどう良くしてくれるのか」というお客さまの期待に応えることは不可能です。
お客さまが知りたがっている原料や成分に対する疑問や質問に応えることは、化粧品への期待値を高めたりお手入れのモチベーションをアップしたりすることにつながるはずなので、通販らしい手法で応えていかなくてはならないはずです。
よりパーソナルに寄り添ったベネフィットで買う

コロナ禍で多くの店販ブランドが通販事業に参画し、競合対策は全方位を網羅しなくてはなりません。競合が増えれば当然、新規売上は厳しくなり、おまけに原料や流通コストまで上がって商品の値上げも避けられなくなってきているのが現状です。
その中で、美容知識を蓄え、よりシビアになったお客さまたちが求めているのは、「モノ(商品)+情報(自分に合うコト)」なのです。

先日実施したグループインタビューでも、「オンラインでカウンセリングをしてほしい」と発言した60代女性がいらっしゃいました。彼女たちが求めているのは、不特定多数のユーザーに向けた一般的な情報ではなく、「自分の肌に何をしてくれるのか?」「自分はどうなれるのか?」という、あくまでも自分事のベネフィット1が知りたいのです。
通販だからといって商品を届けているだけでは、今後は生き残っていけないでしょう。商品+プラスアルファのサービスとして、店販に匹敵するほどのカウンセリング力(相談・問診・ヒアリング)と、お客さまのニーズを引き出し、一人一人に適した商品を案内する提案力、そして顧客ベネフィットを満たす商品の魅力やお手入れ方法を伝授するアドバイス力を兼ね備えたプロの美容部員を育成する必要があります。
そのためには、美容成分だけに頼るのではなく、ブランド独自の美容メソッドを確立して他社との差別化を明確にすること。また、美容部員を含む全社員、スタッフの知識レベルや認識を統一していくことが大切です。

鯉渕登志子
フォー・レディーでは、貴社の課題やお困りごとに寄り添いながら、「店販に負けないサービスの企画・開発」のを支援し、実務に即したトータルサポートをさせていただきます。
用語解説
- ベネフィット―商品を通じて得られる、自分にとっての嬉しい変化や実感できる価値 ↩︎









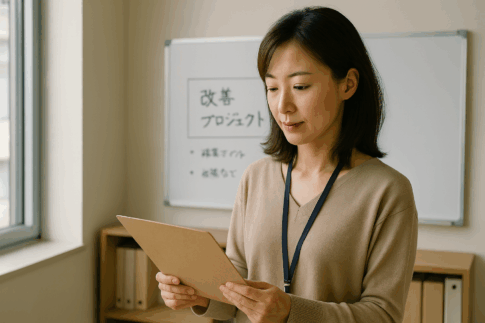







忙しくてなかなか文章を読む時間がない方向け、スキマ時間に聞くだけで学べる音声版をご用意しました。